こんにちは、啓太です。
先日、自宅でずっと使い続けていた桧(ヒノキ)のまな板の削り直しをしました。
桧のまな板の良いところは削り直せば綺麗な面が出てきて、新品同様に使い続けることができるところです。
しかし、削り直すといっても家に鉋(かんな)が置いてある家は多くないでしょう。ましてや鉋を扱える人はさらに少数になります。
誰かに頼むといってもどこに頼めばいいか分からない。
正しいメンテナンスをしないと黒いシミができたり、カビが生えてきたり。
そんな背景もあり一般家庭で木のまな板を使う人は減っている傾向にあるように感じます。
桧のまな板は手入れさえすれば永く使える立派な家庭の道具になります。
今回は、過去に家具工房で働いていて毎日のように木に触れ削っていた経験のある私が、桧のまな板の扱い方を解説していきます。
自然素材を使うには心のゆとりが必要

桧のまな板は当然、自然の産物です。
それゆえに自然素材を上手く使うには使い手の心にゆとりがないと、使うのは難しいのではないかと私は思います。
木は温もりと安らぎをもたらしてくれる反面、そのメンテナンスには注意が求められます。
たとえば、桧のまな板は水分に敏感であり、適切な乾燥が不可欠です。
また、定期的な削り直しやオイルメンテナンスは、桧のまな板を清潔で美しい状態に保つためには欠かせない作業です。
しかし、これらの作業を適切に行うためには少しの技術と時間が必要です。
これは日常の忙しさの中で、心のゆとりを持って桧のまな板に向き合う時間を持つことになります。
桧のまな板を上手く使いこなし、長く愛用するためには桧のまな板の良さを理解し、適切なメンテナンスを心がけることが重要です。
さらに、桧のまな板のメンテナンスを楽しむ心構えも大切です。
削り直しやオイルメンテナンスは、桧のまな板とのコミュニケーションともいえる時間です。
この時間を楽しむことで桧のまな板との関係はさらに深まり、より良い使い心地と長寿命を得ることができます。
削り直しを請け負ってくれるのはどこ?

桧のまな板の削り直しを請け負ってくれる場所はいくつかあります。
以下にいくつかのサービス提供者を紹介します。
杉本木工々房
杉本木工々房は、木のまな板の削り直しを提供するサービスで、全国からの依頼を受け付けています。
まな板を全国どこからでも送ることができ、返送料金込みで2180円からサービスを利用することができます。
また、このサービスは石川県輪島市にある工房で直接まな板を持ち込んでも利用することができます。
庖丁工房タダフサ
庖丁工房タダフサでも、長年使用した木のまな板の削り直しを請け負っています。
顧客はまな板を梱包し、庖丁工房タダフサまで送ることでサービスを利用することができます。
いたみどう
いたみどうは、まな板削り専用切削機を使用して新品同様の平らな仕上がり面を提供するサービスを提供しています。
このサービスはコスト削減、素早い納品、衛生上の悩みのサポート、および環境問題への貢献を提供すると説明されています。
これらのサービスのいずれも、桧のまな板の削り直しを専門に行っているようで、依頼者は自宅からまな板を送ることでサービスを利用することができます。
また、地域によっては直接工房にまな板を持ち込んでサービスを利用することも可能です。
桧のまな板の良いところ

桧のまな板は、その独特の美しさと実用性から多くのキッチンで愛用されています。
以下に、桧のまな板の良い点をいくつか挙げます。
- 自然な素材
- 耐久性
- 包丁に優しい
- 衛生的
- 環境に優しい
- 使い心地
自然な素材
木のまな板は自然素材であり、その温かみと美しい木目がキッチン空間に自然な雰囲気をもたらします。
この自然な美しさは、他の合成素材のまな板では得られないものです。
耐久性
適切なメンテナンスを行えば、木のまな板は非常に長持ちします。
特に、削り直しを行うことで、木のまな板は新品同様の状態に戻すことができ、長期間にわたって使用することが可能です。
包丁に優しい
桧のまな板は、包丁の刃を優しく受け止め、包丁の刃を長持ちさせます。
これは、プロの料理人や料理愛好家にとって非常に重要な点です。
衛生的
適切に乾燥と清掃を行えば、木のまな板は衛生的に保つことができます。
木の自然な抗菌性が、菌の繁殖を抑制し、キッチンを清潔に保つ手助けとなります。
環境に優しい
木は再生可能な資源であり、木のまな板はエコフレンドリーな選択となる可能性があります。
また、適切にメンテナンスを行えば、木のまな板は非常に長持ちし、使い捨てのプラスチック製品と比較して環境に優しいと言えます。
使い心地
桧のまな板は、その重量感と安定性から、料理中に安定したカットを提供します。
また、木の自然な質感は手触りが良く、料理をより楽しむことができます。
桧のまな板はこれらの利点を活かして適切に使用とメンテナンスを行うことで、長期間にわたりキッチンでの信頼できるパートナーとなります。
桧のまな板の悪いところ

桧のまな板は多くの利点を持っていますが、いくつかのデメリットも存在します。
以下に桧のまな板の悪い点をいくつか挙げます。
- メンテナンスが必要
- 水分に敏感
- 重い
- コスト
- 菌の繁殖
- 吸水性
メンテナンスが必要
木のまな板は定期的なお手入れが必要であり、これには時間と労力が必要です。
例えば、削り直しやオイルでの保護が必要となることがあります。
水分に敏感
木は水分に敏感で、濡れた状態で放置すると変形や割れ、カビの発生の原因となる可能性があります。
重い
木のまな板は他の素材に比べて重く、特に大きなサイズのものは移動や収納が困難になることがあります。
コスト
高品質の木のまな板は、プラスチックや竹など他の素材に比べてコストが高くなる場合があります。
菌の繁殖
木のまな板は適切な清掃と乾燥が行われないと菌の繁殖に繋がる可能性があり、これは食品の安全性に影響を与える可能性があります。
吸水性
木は吸水性があり、これが木のまな板が水や食材の液体を吸収し、清掃が困難になる原因となる可能性があります。
桧のまな板のこれらのデメリットは、適切なメンテナンスと注意を払うことで緩和または克服することが可能です。
しかし、これらの点は桧のまな板を選択する際に考慮する重要な要因となります。
おすすめできる人

桧のまな板は特定の利点を提供するため、以下のような方々におすすめできます。
料理愛好家やプロのシェフ
桧のまな板は包丁に優しく、長期間にわたって包丁の切れ味を保持する助けとなるため、料理愛好家やプロのシェフには特におすすめです。
自然素材を好む人
桧のまな板は自然の温かみと美しさを提供するため、自然素材を好む人には良い選択です。
環境に配慮する人
木は再生可能な資源であり、桧のまな板は適切にメンテナンスされた場合、非常に長持ちするため、環境に配慮する人におすすめです。
長期的な投資を考える人
初期投資は高いかもしれませんが、適切なメンテナンスで桧のまな板は数年にわたって使用することができます。これは長期的にコスト効率が良い投資となる可能性があります。
キッチンの装飾を重視する人
桧のまな板はその美しい木目と自然な外観でキッチンの装飾に貢献し、キッチン空間をより魅力的にします。
手入れやメンテナンスを楽しむことができる人
桧のまな板のメンテナンスは少々手間がかかる可能性がありますが、これを楽しむことができる人にとっては、桧のまな板は満足のいく選択となる可能性があります。
桧のまな板はこれらの利点を評価し、メンテナンスに関する必要なコミットメントを理解している人にとって、非常に有益で満足のいく選択となる可能性があります。
お手入れ方法

桧のまな板のお手入れはその美しさと機能性を維持し、長く使用するために重要です。
以下に基本的なお手入れ方法を示します。
- 日常の清掃
- 定期的なオイル処理
- 削り直し(必要に応じて)
- 抗菌処理
ステップ1: 日常の清掃
- 洗浄:
- まな板を使ったらすぐに、亀の子たわしを使って手洗いします。
- たわしでこすることにより、木の繊維に入り込んだ食材の残りや油を取り除きます。
- すすぎ:
- きれいにすすぎます。
- たまに熱湯をかけて消毒します。
- 乾燥:
- まな板を立てて、完全に乾燥させます。
ステップ2: 定期的なオイル処理
- 準備:
- まな板が完全に乾いていることを確認します。
- メンテナンスに使うオイルを用意します。
この時に使うオイルは乾性油である亜麻仁油やエゴマ油などが適しているでしょう。
- オイル塗布:
- ミネラルオイルをまな板の木口に塗布し、布またはペーパータオルを使って木口に軽くこすり込みます。

ステップ3: 削り直し(必要に応じて)
- 削り直しサービス選択:
- まな板が傷だらけで凹凸がある場合、専門の削り直しサービスを利用することを検討します。
- 削り直し手続き:
- 削り直しサービスの指示に従って、まな板を送り、削り直しを依頼します。
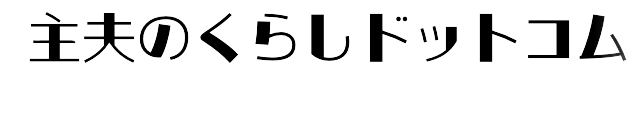




コメント